
何が出題されている?
出題形式:誤っているものを選択
国民年金の保険料免除に特化して出題されます。
- 法定免除の対象者は誰か
- 誰が所得審査の対象になるか
- 学生納付特例(通称、”学特”)と申請免除の関係は
- 産前産後保険料免除
というような定番の知識が出題されます。
スポンサーリンク
過去10回の正解となった知識
- 2025春 遺族基礎年金受給者は法定免除に該当しない
- 2024秋 風水害で損害を受けた場合に免除となる
- 2024春 納付猶予制度では本人と配偶者が審査対象となる
- 2023秋 生活扶助を受けている者は、法定免除に該当する
- 2023春 多胎妊娠の産前産後免除期間は出産日の属する月の3ヶ月前から6ヶ月間
- 2022秋 本人・世帯主・配偶者それぞれに対して所得審査をする
- 2022春 遺族基礎年金受給者は法定免除に該当しない
- 2021秋 学生納付特例制度では本人のみが審査対象となる
- 2021春 生活扶助を受けている者は、法定免除に該当する
- 2020秋 出産日の属する月の前月から納付が免除される
傾向としては、法定免除と誰が所得審査の対象になるかが多く正解になっています。
出題傾向から年金制度を考える
ここはよく正解になる鉄板4つを押さえることです。
- 法定免除の知識
- 誰が所得審査の対象になるか
- 学生納付特例と申請免除の関係は
- 産前産後保険料免除制度
鉄板1 法定免除の対象者
法定免除は、法律で定められた状態の人は所得を審査することなく、届出することで免除を受けられるというもの。
これまで見たことがある肢は、
- 遺族基礎年金受給者が法定免除に該当するか
- 障害基礎年金受給者が法定免除に該当するか
- 生活保護法による生活扶助を受けている者は法定免除に該当するか
の3つ。
年金受給者で法定免除に該当するのは”障害基礎年金”受給者だけです。
遺族基礎年金受給者は法定免除となりません。
生活保護法による扶助は様々ありますが、その中でも「生活扶助」を受けていなければ法定免除とはなりません。
2021春、2023秋では「申請免除者」になるとのことで正解になりました。
生活扶助”以外”の扶助の場合は申請免除を利用できますが、生活扶助の場合は法定免除。
細かいところですが、区別して押さえます。
鉄板2 誰の所得審査をするのか
国民年金の保険料の納付義務者は最大で3人です。
本人・配偶者・世帯主
この3人の所得がそれぞれ基準以下であるかどうかが審査されます。
そして、
学生特例と納付猶予制度は免除が認められずに未納になってしまう不都合を回避するために作られた特別な制度。
例えば、
学生本人に所得が無いのに、同居の親(世帯主)に所得があるという理由で免除が却下になり、滞納につながります。
ですので、これら2つの制度は審査基準を緩くしているわけです。
表でまとめました。○がついていると審査の対象になるということです。
| 本人 | 配偶者 | 世帯主 | |
| 申請免除 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 50歳未満納付猶予 | ◯ | ◯ | |
| 学生納付特例 | ◯ |
正解不正解に関係なく、毎回必ず選択肢の中に並んでいる重要鉄板テーマです。
必ず誰の所得が審査されるのかを覚えなければいけません。
2022秋は3人を合算して審査するという出題がありました。
違います。
1人1人基準に合うのか審査するという仕組みです。
鉄板3 学生は申請免除の利用はできない
学生納付特例が利用できる場合は、申請免除の利用はできません。
特例のハードルを特別に低くして簡単に利用できるようにしているからです。
本人だけの所得審査しかありませんから。
特別に優遇された措置を受けられるので、代わりに申請免除の利用はできないことになっています。
そもそも、
この制度は平成3年4月から平成12年3月までの”学生免除制度”の不都合を改めたものです。
この学生免除制度、要は全額免除と同じで3分の1が国庫負担で年金額に反映するというものでした。
ただし、
所得の審査が世帯主にもあったので、
親の所得が多いから却下 → 未納 → 障害年金不可
という問題が生じていました。
同じ問題が生じてしまうので、通常の申請免除制度は利用できないのです。
2022春は久しぶりにこの肢が復活。
しばらく消えていたのです。
代わりに登場していた引掛けとして、2021秋、2022秋には
50歳未満の保険料納付猶予制度の対象(略)者でも、保険料半額免除の申請をすることができる
答えは 正しい です。
納付猶予制度対象者は申請免除を利用できない なんてことは条文上どこにも書いてないからです。
鉄板4 産前産後免除制度も必ず出る!
2019年4月から施行された産前産後免除制度。
出題が続いています。
数字が絡んでいるので問題も作りやすいですし。
押さえておくべき知識は以下のとおり。
- 出産予定日・出産日の属する月の前月から4カ月間が免除される
- 多胎妊娠の場合は出産予定日・出産日の属する月の3カ月前からの6カ月間が免除される
2021春、2022春、2022秋、2024秋は”1”が出題されましたが正解にはなりませんでした。
2020秋は「前月」ではなく、当月から免除ということで誤り。
2021秋、2023秋、2025春は、”2”の多胎妊娠の場合が出題。
いつから4カ月間、6カ月間かをしっかり押さえます。
詳しいことは、以前コラムでまとめたことがあるので参考にしてください。
-

-
施行まで半年!産前産後期間の保険料免除は免除じゃないってどういうこと?|みんなのねんきん
どんなニュース?簡単に言うと 2019(平成31)年4月から施行される国民年金の第1号被保険者の産前産後の保険料免除。施行半年前の2018年8月、厚労省より政令と省令の改正が発表されました。これを期に ...
続きを見る
ちなみに私は数字を覚えるのではなく、1の”前月から4ヶ月間”を図でイメージして、多胎妊娠の場合は”その前月にプラス2ヶ月前”と、2ヶ月分のブロックを”前月”にくっつけるという感じで覚えています。
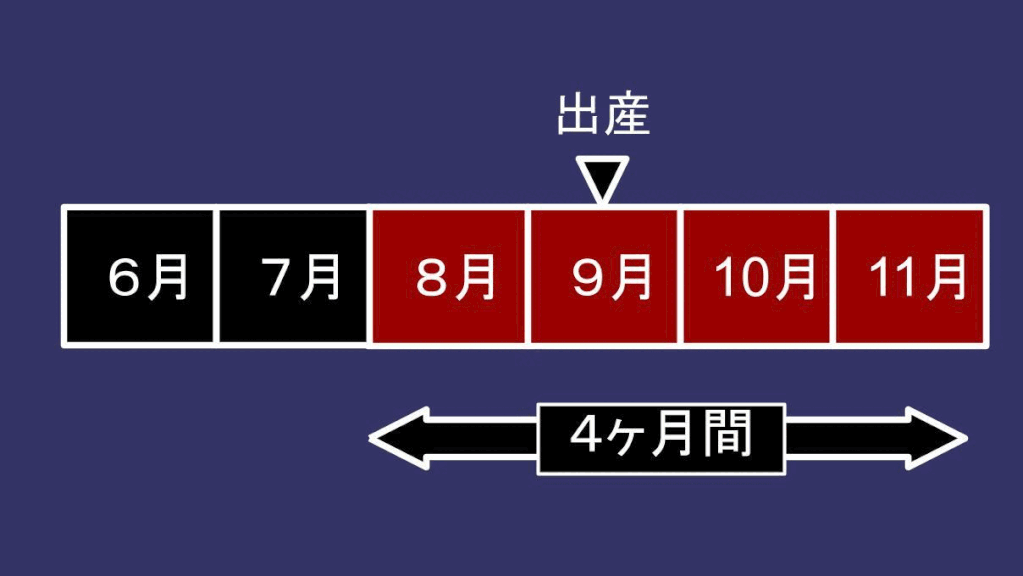
また、2024春は数字に絡んだ問題ではなく、免除の承認を受けた期間は産前産後の免除の対象となるか?という出題がありました。
例えば、7月に翌年6月に掛けて半額免除の承認を受け、翌年3月に出産した という場合は、2月から5月までの4ヶ月間は免除期間ではなく、保険料納付済期間となります。
免除の方が優先されるわけではないので注意です。
まとめ
最近は敢えて、過去正解になっていない知識から無理やり出題するような傾向が見られます。
予想は難しい状況です。
ただ、上に取り上げた4つの鉄板知識は仮に正解にならないまでもほぼ確実に選択肢の1つとして並んでいます。
- 法定免除の対象 → 障害基礎年金受給者、生活扶助を受けている者
- 誰が所得審査の対象になるか → 本人・配偶者・世帯主 全員か?一部か?
- 学生納付特例と申請免除の関係は → 学特使えるなら申請免除使用不可
- 産前産後保険料免除 → 前月から4カ月間、多胎なら+2ヶ月前
これらの知識から消去していけば正解にたどり着けます。
どれが正解になるか予想するよりも、4つの鉄板知識を押さえる方向でいきましょう。






シモムー
みんなのねんきん主任講師