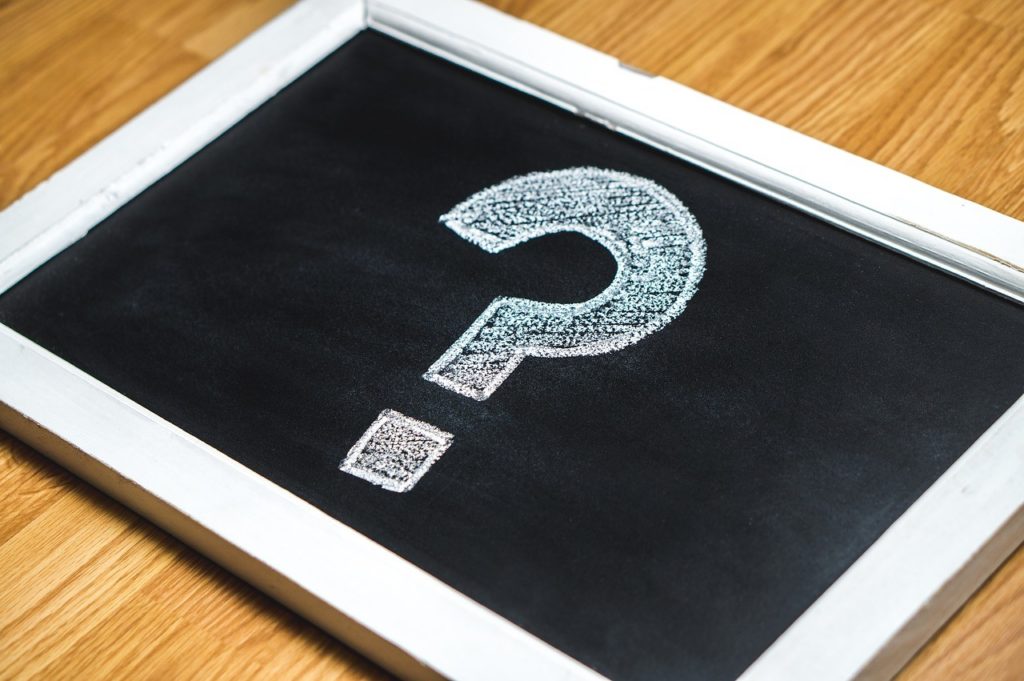
年金アドバイザー3級試験ってどんなの?
「勤務先から受けるように言われたんだけど・・・」
「社労士試験で役に立つと言われたんだけど・・・」
あなたがこの記事を読んでいるということは、こんな疑問をお持ちですよね。
1回合格すれば2度も受ける必要がない試験にひたすら20回以上受験し続けてきた私シモムーが、改めて「3級試験ってどんなだ?」と振り返ってみました。
今回は、試験が想定する対象者とコンセプトについて。

という方に役立つようまとめてみます。
敵を知ることから始めましょう!
スポンサーリンク
年金アドバイザー3級試験はどんな試験か
試験の沿革は?
この試験は、銀行業務検定協会が実施する民間の試験です。
3級試験が最初に登場し、次いでその上の2級、その下の4級が作られたという経緯があります。
(4級と2級はどっちが先かは忘れましたが、とにかく3級が最初です)
4級=初級、3級=中級、2級=上級 という位置づけのようなので1級は存在しません。
3級の登場は1990年代だった気がします(何かで読んだのですが忘れました)。
2020年11月からはCBT試験(パソコン上で受験する)形式が始まりました。
誰のための試験?
ここからが大事です。
一体誰のための試験なんでしょうか。
答えはここに出ています。
金融機関の営業店に勤務する窓口・渉外担当者等を対象に、公的年金等に関する基本知識や顧客からの年金相談に応じ、適切なアドバイスを行うための実践的応用力等について、その習得程度を測定します。
(出典:経済法令研究会ウェブサイト 試験申込みページ)
ここからわかることは、試験の対象者が、金融機関の窓口・渉外担当者 であることです。
最初私は「年金っていうぐらいだから受験者はシニアが多いかな?」と思っていたのですが、全くの誤解。
試験会場には金融機関勤務の若手の人たちで溢れています。
こういった方々が昇進昇格の条件の一つとして受験を課せられているようです。
ですが、受験者層を見てみると、必ずしも金融機関勤務の人のみが受けているわけではありません。
実は全体の3分の1が無所属の「個人受験者」なんです(私も含めて)。
昇進昇格に無関係の個人がなぜ受けているのか。
それは試験の中身にヒントがあります。
どんなコンセプトの試験?
個人受験者が一定程度いる理由
上の試験の説明をよく見てみると「公的年金等に関する基本知識や顧客からの年金相談に応じ、適切なアドバイスを行うため」となっています。
つまり、専門家のような深い知識を判定しようという試験ではないということ。
実際に私が受験を続けて思うのは「広く・浅く問われているな」と感じます。
「広く・浅く」ですから、試験のための勉強が、結果的に「年金制度の基礎的な全体像を把握できる」効果をもたらしています。
個人受験者が一定の割合いるのはこういうわけです。
こういった人たちは年金の基本知識を純粋に高めたいという人たちのはずです。
ちなみに、私は昇進昇格のためでも社労士受験のためでもありません。
「年金知識を維持させるために定期的に受ける」という趣旨で、定期健康診断みたいな感じです。
あとは、年金の実力を認知してもらうための実績づくりというのもありますが・・。
こういう受験動機の方は数千人以上いる受験生の中でも私くらいなんじゃないかと思っています。
また、
「実践的応用力等について、その習得程度を測定」とあるので、技能・応用のパートがあるわけです。
たしかに、出題の内容を見ると、年金請求書の書き方に関するものや年金受取口座の変更届の注意点といった実践的な出題もされます。
こういった点から、やはりこの試験は基本的には金融機関の人のためのものであるなと感じます。
社労士試験受験生が3級を受けた方が良いか
社労士資格の受験予備校で講師をしている時代に「3級を受験した方が良いですか?」とよく訊かれました。
もし今、同じ質問をされた場合、「年金が好きなら受けてもいいんじゃない」と答えます。
好きならより一層知識を高めて得意科目にできると思います。
しかし、そもそも年金が苦手というなら社労士試験にも悪影響が出るのでやめたほうがいいでしょう。
(2つの試験を両立させて合格するのは甘くありません)
社労士試験には無関係な知識も結構含まれていますから(年金受取りの金融機関変更の注意点なんて出題されません)。
ですから、社労士試験には間接的には役に立つけど、直接役に立つというものではないといえます。
年アド3級が社労士試験の論点を意識して問題を作っているわけでは無いですからね。
まぁ、3級受験は社労士試験に合格してからでも良いのではないでしょうか。
私もそうでしたから(ま、私は年アド試験なるものをそもそも社労士受験中は知らなかっただけですけど)。
まとめ
年金アドバイザー3級試験はどんな試験?
まずは、誰のための試験でどんなコンセプトなのかという点でまとめてみました。
- 金融機関の窓口・渉外担当者向けの試験 若い人がたくさん受験会場に
- 「広く・浅く」出題されるため、年金制度の基礎的な全体像を把握できる
- 一定割合の個人受験者 年金の基本知識を高めたい人たちも受けている
20回以上受験してきたなかで思うのは、「俺って年金が好きなんだなぁ」ということ。
そうでなければここまで続けることはできませんでした。
年金って細かい点でどんどん中身が変わりますから常に知識のメンテナンスが必要なんです。
ところで、受験生の中には「受けろと言われたからやむなく受ける」という人もいるでしょう。
でもせっかく受験する機会があるわけですから、そこから何か少しでも持ち帰ってやろうという視点でやってみてはどうでしょう。
好き嫌いにかかわらず、年金が無関係な人っていません。
その知識が必ず役に立つと断言できます。

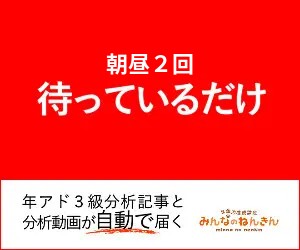



シモムー
みんなのねんきん主任講師