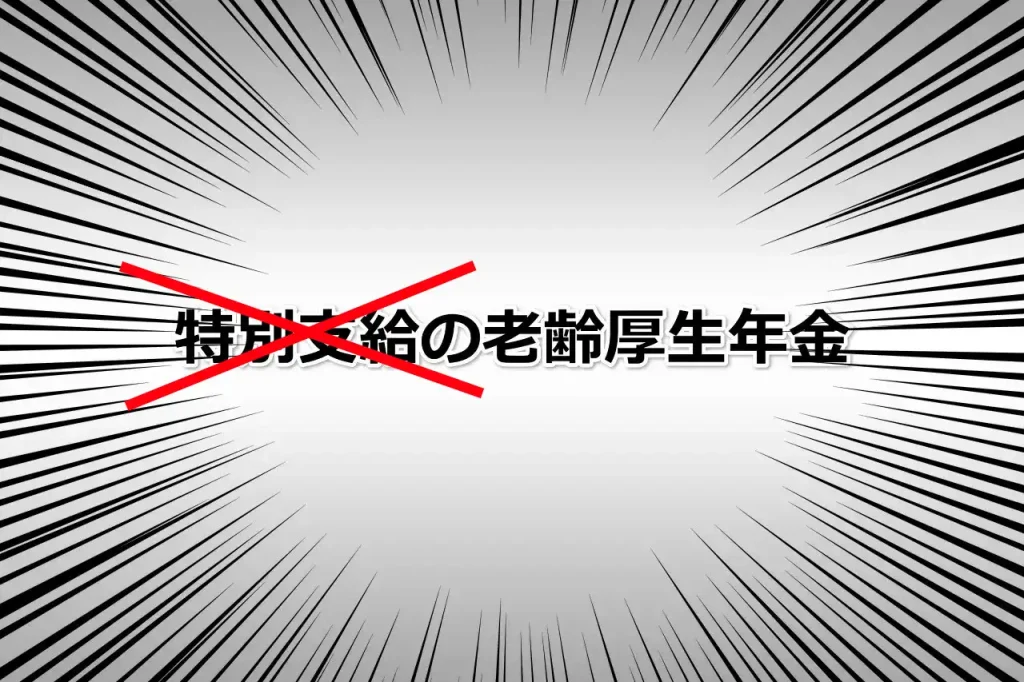
何が出題されている?
出題形式:正しいものを選択(2023秋まで)、誤っているものを選択(2024春、2024秋、2025春)
2024春までは60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金:以下「特老厚」)について出題がされていました。
2024秋からは「特別支給の老齢厚生年金および老齢厚生年金」というテーマで出題。
今後は老齢厚生年金全般の知識を問う出題が続くと予想します。
スポンサーリンク
過去10回の正解となった知識
- 2025春 受給資格期間を満たし、被保険者期間が1年以上あれば支給される
- 2024秋 65歳からの老齢厚生年金は65歳に達した月の翌月分から支給される
- 2024春 長期加入特例の「44年以上」は複数の種別の被保険者期間を合算しないで判定する
- 2023秋 受給資格期間を満たし、被保険者期間が1年以上あれば支給される
- 2023春 特老厚の受給権は65歳で失権する※
- 2022秋 被保険者である間、定額部分は支給されない
- 2022春 障害等級3級の状態にあり、退職していれば定額部分も支給される
- 2021秋 被保険者期間が44年以上あり、退職していれば定額部分も支給される
- 2021春 男性の支給開始年齢の判定
- 2020秋 報酬比例部分を通常通りに受給すれば老齢基礎年金はいつでも繰上げできる
メモ
※2023春は「特別支給の老齢厚生年金」とするところ、「特別支給の厚生年金保険」として出題されました。不正確な記述のため全員正解として処理されました。
よく正解になる特老厚の知識は以下の3つ。
- 障害等級3級の状態にあり、退職していれば定額部分も支給される → 障害者特例
- 被保険者期間が44年以上あり、退職していれば定額部分も支給される → 長期加入特例
- 受給資格期間を満たし、被保険者期間が1年以上あれば支給される → 特老厚の支給要件
3つの知識をしっかり押さえておけば正解にたどり着けるでしょう。
特に太字の箇所が問われます。
出題傾向から年金制度を考える
支給開始年齢の注意点
かつては問題文中に生年月日の設定があったのですが、現在は特老厚を含めた”老齢厚生年金”の出題なので設定がなくなっています。
ただ、「試験日現在60歳」という表現で出題はあるので令和7年10月で60歳に達する人を確認しておきます。
- 特老厚を新たに受給できるのは1号厚年期間のある女性のみ
- 支給開始年齢は報酬比例部分のみを64歳から
- 報酬比例部分の支給がされる前までに繰上げ請求が可能
- 1号厚年期間がない女性には特老厚が支給されない
男性は年齢引き上げが完了し女性の支給開始年齢は既に64歳。最終段階になりました。
生年月日からの支給開始年金の思い出し方は以下のテクニックを押さえておきましょう。
-

-
【限定公開】解法テク1 年金アドバイザー試験のための特老厚の支給開始年齢を鼻歌を歌いながら思い出す方法|みんなのねんきん(3級対策限定特典)
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
定額部分がもらえる特例
定額部分が支給される特例の知識については以下の項目を押さえておけば足ります。
- 特例に該当しても報酬比例部分がもらえる年齢にならないと定額部分の加算はない
- 44年以上加入した長期加入者・障害者共に厚生年金の被保険者でない(退職している)こと
- 障害者の場合は3級状態でも該当する
特に、被保険者になっている(在職者)は特例に該当しない
という条件はよく間違いを作る箇所ですからしっかり注目。
最近では2021秋、2022春、2022秋の3連続で正解となっています。
ただ、”老齢厚生年金”のくくりでの出題となってから出題がなくなってしまいました。
繰上げと1年以上の支給要件も大事
特老厚の支給開始年齢と定額部分開始の特例の2大分野以外では
- 報酬比例部分を繰り上げる場合は老齢基礎年金も一緒に繰り上げる
- 支給要件として被保険者期間が1年以上必要
も注意です。
繰上げは老齢基礎年金の扱いに注意
前者は、
老齢基礎年金は65歳から受給できる
と、まるで老齢厚生年金と老齢基礎年金を別々に繰上げできるかのような肢が並んでいるのでしっかり注意。
老齢厚生年金を繰り上げると老齢基礎も一緒に繰り上がってしまいます。
この話は、つまり”経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金”の受給です。
これは詳しくは技能・応用で出るテーマなのでそちらで詳細を理解しておきます。
-

-
【2025秋最新版】年アド3級 技能応用 老齢年金の繰上げ 特老厚が出ない人はどうなる?|みんなのねんきん
過去の出題傾向からシモムーの感想 このテーマは繰上げに関するものですが、時代によってその仕組みが変わるのでそれに合わせて出題の事例も変わるという特徴があります。 2024春までは特別支給の老齢厚生年金 ...
続きを見る
2020秋はちょっと変わった形で繰上げに関する論点が出題。
報酬比例部分を通常通りの年齢で受け取り、老齢基礎年金を同時に繰上げ受給できるか?
というもの。
これはできます。
報酬比例部分を通常の支給開始年齢で受け取り始めさえすれば、その後は老齢基礎年金を別に繰上げ可能(もちろん繰上げなくても良いです)。
反対に、報酬比例部分を繰上げた場合は、老齢基礎年金も同時に繰上げないといけません。
支給要件の「1年」を「1ヶ月」とするのは頻出
特老厚の支給要件は誤りの肢を作る場合は”1カ月以上”として登場させます。
1年(12カ月)以上必要なのは特老厚の支給要件。基本中の基本です。
よくこの形で誤りを作るのでしっかり頭にいれます。
特老厚を繰下げ受給できる?
2023春、2023秋、2024春は特老厚を繰下げ受給できるのか?というものが出題。
”特老厚を受け取らずに我慢すれば増える” → 世間ではよくある誤解ですが、これはできませんね。
繰下げできるのは65歳からの本来支給の老齢厚生年金のみです。
被用者年金一元化の論点
2024春は被用者年金一元化(共済年金と厚生年金の統一)に関する出題がありました。
今後も出題があるかどうかはわかりませんが、出たものは必ず押さえておきます。
- 2から4号厚年の女性は男性と同じスケジュールで支給開始年齢が引き上がる
- 長期加入特例の「44年以上」は複数の種別の被保険者期間を合算しないで判定する
2025春は3号厚年のみの方の出題だったので、特老厚は出ない(正しい)という出題でした。
また特老厚の1年要件については、以下のものも押さえておきましょう。
- 支給要件である「1年」は複数の種別を合算して判定する
特老厚絡みの被用者年金一元化の論点はこの程度で対応できると思います。
まとめ
今後は特老厚単独での出題に戻ることはないと思います。
問われる論点が無さすぎるからです。
2024秋で出題された 特老厚+老厚 の形で徐々に 老厚 のテーマに切り替わっていきそうな気配。
ただ、2024秋の老厚の論点はここで取り上げる必要がないほど基本的なものでした。2025春も同様です。
まずは、これまでの特老厚の論点である3つを確実に押さえます。
- 障害等級3級の状態にあり、退職していれば定額部分も支給される → 障害者特例
- 被保険者期間が44年以上あり、退職していれば定額部分も支給される → 長期加入特例
- 受給資格期間を満たし、被保険者期間が1年以上あれば支給される → 特老厚の支給要件
他の論点はしばらく出題の状況を見ないとなんとも言えないです。







シモムー
みんなのねんきん主任講師