
何が出題されている?
出題形式:誤っているもの選択 と 正しいもの選択(2020秋)
確定拠出年金(「DC」として表記することもあります)に関するあらゆる知識が網羅的に出題されています。
普段は誤りを探す問題なのですが、”正しいものを選べ”で出たこともあります。
どちらの形式の出題なのか、必ず確認しないといけません。
特にこのテーマは近年、改正が続いてその点でも大事。
2017春からは「個人型」限定で出題がされていますから「企業型」は気にする必要はありません。
基本知識問題の終盤問題の中でも改正が重なる難易度の高いテーマと言えます。
スポンサーリンク
過去10回の正解となった知識
- 2025春 企業型と同時に個人型にも加入できる
- 2024秋 20歳前でも厚生年金の被保険者は加入対象者となる
- 2024春 保険料の一部免除を受けると掛金を拠出できなくなる
- 2023秋 企業年金を実施しているとイデコプラスは実施できない
- 2023春 加入時にマイナンバーの提出は必要ない
- 2022秋 給付の種類は、老齢給付金・障害給付金・死亡一時金である
- 2022春 iDeCo+は従業員のiDeCoの掛金に事業主が掛金を上乗せする仕組み
- 2021秋 老齢給付金は一時金で受け取れる
- 2021春 掛金額の変更は1年に1回限りである
- 2020秋 運営管理機関の変更時は運用商品を解約しなければならない
すべての回で異なる知識が正解になっているのがやっかいなところ。
大きく分類してみると、
- 加入の対象者になるかならないか
- 運営管理機関のルール
- 掛金の取扱い
- 給付金の内容・受取方法
が問われていることがわかります。
初めて出る知識も並ぶ可能性が高いので、その点で怖いテーマ。
毎回分析しながら私自身も勉強しているような状況です。
出題傾向から年金制度を考える
正解が毎度バラバラですから、地道に重要知識を1つ1つ理解していくしかない、近道のない問題といえそうです。
近道は無いとはいえ、過去の正解はヒントになります。
これら、過去に正解に関係した制度の解説をしていきましょう。
私が年金制度を整理するうえで意識している「入る」「納める」「もらう」で分けてみます。
確定拠出年金は他の年金と根本的にどう違うのか
まず、総論として、確定拠出年金の性格から。
制度のネーミングのとおり、納める掛金だけが確定している。
将来の給付額は運用結果次第という、ある意味わかりやすい仕組みです。
反対に”確定給付型”は将来の給付の内容を約束しているので、現時点で積立が必要額に足りなければ実施主体が補填しなければいけない。
これが無いのが確定拠出年金を実施する側のメリットです。
”お得な仕組みだから使わなきゃ損!”と盛り上がっています。
実態は運用の知識が無い素人の加入者に責任を転嫁する仕組み。
運用結果は自己責任ということを覚悟しておかないといけません。
確定拠出年金の「入る」
メモ
以下、個人型の出題しかありませんので企業型の説明は割愛します。
個人型の実施主体と加入者
実施主体
実施主体は国民年金基金連合会です。
最近は出題はありませんが、かつてはこれがそのままよく出題されていました。
加入者の範囲
かつては国民年金の第3号被保険者、公務員、企業年金加入者は加入できませんでした。
現在はほぼ全ての公的年金加入者が加入できるようになっています。
また、2022年5月からは更に加入できる範囲が広がったので注意。
- 60歳以上の国民年金被保険者であれば65歳に達するまで加入可能
- 日本国籍を有する海外居住者は国民年金の任意加入被保険者になれば加入可能
前者の60歳以上の国民年金被保険者とはすなわち、第2号被保険者と任意加入被保険者のことです。
さらに、
2022年10月からは、企業型に加入しつつ個人型にも入る要件が緩和されました。
従来は、企業型の規約にiDeCo加入を可能とすることが明記されていることが必要でしたが、企業型DCの規約に定めがなくても、個人型にも加入できるようになりました。
2025春は企業型と個人型の両方には加入できないとの出題がありましたが、両方入れます。
厚生年金の被保険者が加入する場合の年齢制限
厚生年金の被保険者は20歳未満でも国民年金の第2号被保険者になりますね。
それでは、この確定拠出年金にも20歳未満でも入れるのか?と疑問になります。
結論、入れます。
20歳以上というような下限はありません。
2020秋、2021秋はこの点、20歳未満はどうか?という出題がありました。
2024秋はこれがこのまま正解となりました。
年齢条件は正解にしやすいので、しっかり押さえます。
このように、確定拠出年金に加入できる範囲は国民年金の被保険者と連動しているわけです。
この点で、2022秋は初めて
国民年金の被保険者資格を喪失したとき、加入者の資格を喪失する。
という出題がありました。これは正しいということになります。
2024春は
国民年金の被保険者でない者は、加入対象者とされない。
という出題が。これも正しいですね。
保険料免除を受けている期間は加入できない
確定拠出年金は公的年金を補完する私的年金。
まずは公的年金の保険料をきちんと納めていないことには加入できないことになっています。
納めているということは免除を受けている場合もNGということです。
私的年金の趣旨は、公的年金の上乗せで保障を充実させること。
”自助”の原則に従い、公的年金の義務を果たしていなければ上乗せを認めません。
趣旨から考えれば理解ができると思います。
ただし例外があります。
障害基礎年金の受給権により法定免除を受けている場合
には加入できます。
これは障害者への例外的な配慮です。
同じ法定免除でも、生活扶助を受けているための法定免除では加入できません。
2024春、2024秋、2025春は”半額免除を受ける”場合の出題がありました。
障害年金受給による法定免除以外の免除では掛金の拠出はできません。
加入時にマイナンバーの提供は必要か?
2023春に初出題。
またも、聞いたことがない問題が登場しました。
私は自身の経験で、運営管理機関を変更した際になんとなくマイナンバーを記入したような気がしたので”正しい”と回答。
結論、不要ということで間違ってしまいました。
調べたのですが法律上の根拠はわかりませんでした。が、いくつかの運営管理機関のQ&Aには確かに「不要」という回答がウェブサイトに出ていたので、参考までに。
-
-
マネックス証券
続きを見る
-
-
みずほ証券
続きを見る
この肢が誤り(提出不要)とわかったとき、
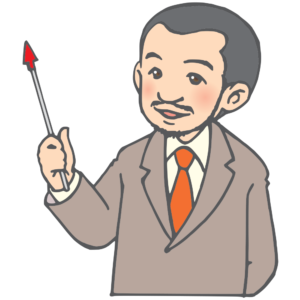
と思ったものです。2023秋も選択肢に並んでいました。
確定拠出年金の「運営管理機関」の役割
2020秋は個人型確定拠出年金の運営管理機関の知識が複数並んでいました。
運営管理機関は一言で言うと、国民年金基金連合会と加入者の間に立って両者を取り持つ組織です。
加入者は個人ですから、国民年金基金連合会が一人一人を相手にしていたら事務作業が煩雑。
そのため、運営管理機関を間に挟んで事務処理を効率化しているわけです。
この機関は加入者への情報提供を行い・加入者からの運用指示を取りまとめて連合会に通知します。
運営管理機関はいろいろな民間企業が参入しており、情報量の違いや手数料の違いで競っています。
一度決めた運営管理機関は途中で変更することが可能で、その際は運用商品を全て解約したうえで新しい運営管理機関で再度運用商品を選び直します。
2020秋、2021春、2022春、2023春はこの運営管理機関の変更について出題がありました。
メモ
私も勉強をしていくなかで、自分がお世話になっている運営管理機関の手数料が高いことがわかり、変更手続きしてみました(もちろん運用商品は一旦全て解約)。変更先の運営管理機関に対して手続きするだけで完了。難しくはありませんでした。
確定拠出年金の「納める」
拠出限度額は月単位から年単位へ
まず、拠出の限度額ですが、月額から年額へと改正により変更となり、2018年1月より施行されています。
これは、前月に拠出限度額の枠内で使い残しがあっても翌月に繰越ができなかった不都合を改めるためのものです。
したがって、「1年に1回以上定期的に」拠出することになっています。
私は従前どおり、毎月1回定期的に拠出しています。
拠出限度額は出そうで出ない
個人型の拠出限度額
拠出限度額は試験では出しやすいと思うのですが、過去の傾向はどういうわけか、数字を直接問う問題は2023春以外はありません。
年アド3級では神経質になる必要は無いというのが過去の傾向です。
| 分類 | (月額) | |
| ①国年1号 | 68,000円 | |
| ②国年3号 | 23,000円 | |
| ③以下国年2号 | 企業年金なし | |
| ④ | 企業型DCのみ | 20,000円 |
| ⑤ | 企業型DC+DB | |
| ⑥ | DBのみ | |
| ⑦ | 公務員 |
上の表で列挙した⑤から⑦は2024年12月から月額20,000円となっています(なお、事業主掛金が35,000円を越えるとこの額を越えた分減少する)。
今回の改正の考え方はこちらのチラシを確認してください。
-
-
企業型DCの加入者がiDeCoを利用しやすくなります
www.dropbox.com
これまでの出題は国年3号の限度額を問うものしかないので、少なくとも月額23,000円だけは押さえておきましょう。
拠出額の下限
上限ばかりに目が向きがちですが、下限にも注意。
最低でも毎月5,000円を拠出するルールになっています。
ここに1,000円単位で上乗せすることが可能。
2020秋、2021春、2022秋で出題がありました。
拠出額の変更
拠出額は変更ができますが、年に一度限り(毎月定額拠出の場合)。
月1回、年12回まで掛金額を変更することができる
と2021春には出題されました。
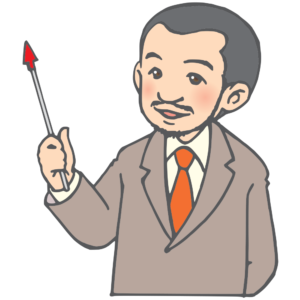
と試験会場でツッコミを入れたものです。
2022春も変更回数のことで出題がありました。
クレジットカードでの支払いは不可能
2019春には初めて見る肢として、クレジットカード払いの可否がありました。
公的年金では国民年金の第1号被保険者の保険料をカード払いすることは可能。
では、個人型DCでは?
無理です。口座振替のみです。
2020春(模擬)はこの点で初の正解となりました。
前納もできない
まとまった額を先に納める前納という仕組みは確定拠出年金にはありません。
国民年金の保険料とは違います。
事業主に納めてもらうか、自身で納めるか
2022春にも初めて見る肢が!
厚生年金に入りながら個人型に入る場合、事業主の口座からの振替か、加入者本人の口座からの振替か、2種類が存在します。
前者の場合は、給料からの天引きで事業主が本人の代わりに納めます。
実務的には最初の手続きの際に、加入者自身が事業主に口座振替をお願いするのですが、その体制が整っていなければ、本人の口座からの振替しか選べません。
個人型はいつでも拠出をやめられる
毎月の掛金を納められそうにない・・
そんな場合は、”拠出をいつでもやめられる”のでご安心を。
老後の資金をコツコツ積み立てて運用する仕組みなのに、そんなの認めちゃっていいの?
と思っていたのですが、可能です。
個人型の場合は連合会に申出をすることでいつでもやめられます。
しかし、掛金の払込を止めても積み立てたお金を返してもらうことはできません(条件に合えば脱退一時金という仕組みがありますが・・)。
今まで積み立てたお金は基本的には老齢給付金として老後に受け取るしかないわけです。
ですので結果的に掛金の拠出をやめれば、あとは積み立てているお金をどう運用するかだけの立場になります。
この立場を”運用指図者”と言います。
そして、運用指図者として70歳になるまで資産運用を継続できます。
運用指図者の定義について、
掛金を拠出しながら運用を指図する
と出題されたことがあります(これは誤り)。
試験会場で私は、
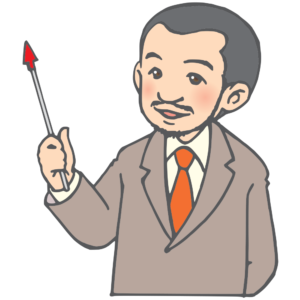
とツッコミを入れたものです。
iDeCoプラスに注意
2018年に創設したiDeCoプラス。
個人型に加入する従業員の掛金に事業主が掛金をプラスできるシステム。
年アド試験では出題可能性が高い分野です。
注意すべき項目をまとめておくと、
- 企業年金を実施していない従業員300人以下の事業主
- 個人型に加入している従業員のうち、事業主掛金を拠出されることに同意した加入者
- 拠出の対象となる従業員に資格(勤続年数など)を設けることが可能
- 事業主掛金のみとする(加入者掛金をゼロにする)ことはできない
最後に列挙した事業主だけが掛金を出すような設定はできないということで2021秋に出題。
2022春も似たような肢で正解。あくまで従業員の掛け金に上乗せする仕組みであることを理解します。
2023秋には「確定給付企業年金」を実施している場合はどうか?という出題で誤り。冒頭にあるように企業年金を実施していたら対象外です。
2024春、秋は連続して事業主掛金と合計で月額23,000円が上限という出題で正しい。
企業年金を実施していない事業主なので、上の拠出限度額の表の③に該当する人。なので、23,000円なのです。
実は私が設立した会社でも導入してみたので経験談も参考にしてください。
-

-
実録!iDeCoプラスを始めたらメリットしかなかった体験記|みんなのねんきん
どんな事例?簡単に言うと・・ 個人型確定拠出年金(iDeCo)にiDeCo+(イデコプラス)という仕組みがあります。 今回、みんなのねんきんの運営会社(一般社団法人次世代ウェブ教育開発研究機構)で導入 ...
続きを見る
確定拠出年金の「もらう」
給付の種類は3種類
給付の内容は
- 老齢給付金
- 障害給付金
- 死亡一時金
の3種類。死亡に関する給付が「遺族給付金」ではなく、「死亡一時金」というところが引っかかりやすいところ。
2022秋で正解となりました。
(当分の間の経過措置ということで 脱退一時金 もありますが、これを入れると4種類となります)
60歳からもらうには10年以上拠出すること
60歳から老齢給付金をもらうためには
10年以上の通算加入者等期間が必要
というもの。
「通算加入者等期間」とは、企業型・個人型での掛金を拠出していた期間(通算拠出期間)と運用指図者の期間のこと。
それらひっくるめて10年以上なければ最速の60歳でもらえません。
他には8年なら61歳で、とか細かくルールがありますが、”60歳からなら10年”だけ覚えておけばよし。
2020秋はこの点で、”65歳からもらうには要10年”と出題され、誤りに。
ちなみに1カ月でも当該期間があれば65歳からもらえます。
2023秋、2024春には60歳以降の期間はどうなる?という出題がありました。
60歳に到達するとその後は通算加入者等期間に算入されません。
通算加入者等期間はあくまで60歳時点で支給開始年齢を決めるための期間といえるでしょう。
60歳過ぎてから初めて加入すると?
上の「通算加入者等期間」の判定は60歳時に行います。
とすれば、
60歳になるまで確定拠出年金に入ったことがなく、国民年金の任意加入被保険者になって併せて個人型に初めて加入し(2022年5月改正で可能)、64歳から拠出を始めたらどうなるでしょう?
この場合は、5年後の69歳から受取可能です。
こういう事例に対応するため、”加入者となった日から5年を経過した日から受取可能”というルールもできました。
数字が絡んでいるのでこの点も危ない感じがします。
受給開始時期が75歳まで引き上げ
2022年4月からは公的年金の繰下げ制度が75歳まで引き上げられたことに伴い、確定拠出年金についても同じく受取可能年齢が75歳までに引き上げられました。
つまり、60歳から75歳までの間で受け取るということ。75歳を過ぎても受取手続きをしていないと強制的に一時金で全額支給されます。
2023春、2023秋、2024春、2024秋、2025春と5回連続で出題中。
ただし、2022年4月の時点で70歳以上の人は対象外。
昭和27年4月2日生まれ以降の方限定である点に注意です。
受取方法は3種類「年金」「一時金」「年金と一時金の組み合わせ」
給付金の受取方法は、
- 年金
- 一時金
- 年金と一時金の組み合わせ
の3種類。
一時金として受給することはできない
という形で出題があります。
ちなみに、
「年金」で受け取る場合は税制上雑所得、「一時金」なら退職所得となり、退職所得として税負担が軽くなる「一時金」が有利などと言わることがあります。
老齢給付金は死亡以外でも失権することがある
生涯受け取れる公的年金の老齢年金とは違います。
この老齢給付金は
- 死亡した
- 障害給付金の受給権者になった
- 個人別管理資産がなくなった
以上の場合で失権します。
”3”の積立てた資産がなくなると失権するというのはさすがは積み立てた結果を受け取る年金ってことで、なるほど〜って感じ。
まさに自己責任の年金です。
死亡一時金まで出題がある!
2023春にはついに死亡一時金の中身が出題!
どこまで初ものを出題させたいのかわかりませんが、とにかくこのテーマは初ものが多い印象。
死亡一時金は故人が積み立ててきた掛金を一時金で受け取る仕組み。
国民年金の独自給付にある死亡一時金と同じく、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が受給できます。
大きな特徴は、受取人を予め指定できること。
国民年金の死亡一時金には無い仕組みです。
まとめ
最近は何が正解になるかわからないこのテーマ。
なにこれ?という知識が出題されるんじゃないかとここ最近はいつもビクビクしています。
直近の2022年の改正は今でも出題が続いているので注意。この点だけ抜き出してみると、
- 60歳以上の国民年金被保険者であれば65歳に達するまで加入可能
- 日本国籍を有する海外居住者は国民年金の任意加入被保険者になれば加入可能
- 企業型に加入しつつ個人型にも入る要件が緩和(企業型DCの規約に定めがなくても個人型加入OK)
- 60歳以降で初めて加入者になったらその日から5年を経過した日から受取可能
- 受取可能年齢が75歳までに引き上げ(昭和27年4月2日生まれ以降の方限定)
それでも、新しい肢が出る可能性が高いので不安であることに変わりはありません。
対策としては、知らないものは△で後回し。
知っている知識だけで勝負する。
前提として、過去問をしっかりやり込んで知っている知識を確実にしてください。
知っているものだけで絞り込んで、最後の2択で間違えてしまったら、それはもう仕方が無いです。
難問攻略法はこれしかありません!








シモムー
みんなのねんきん主任講師