
「質問がある猫は挙手を」「ニャ!」
長年、年金アドバイザー3級対策のアドバイスをしていますが、勉強方法や制度に対する質問が寄せられます。
その都度、丁寧に回答することを心がけていますが、ふと思いました。
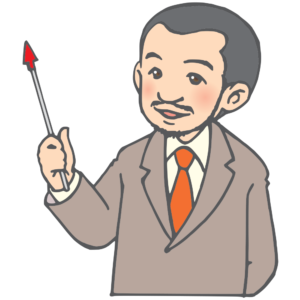
そこで、当ブログをご覧になっている受験生と一緒に、寄せられた質問・私の回答を共有します。
1人の疑問は他の誰かの疑問の可能性があるからです。
それではいってみましょう。
注:ご質問の受付は毎日配信サービスの利用者のみに限定していますのでご注意ください
年金制度に関する質疑応答
NEW Q 寡婦年金と遺族厚生年金との併給調整
(2023年春問43について)寡婦年金と遺族厚生年金の併給について、なぜ併給されないのでしょうか。国民年金と厚生年金とで制度が違うので併給されるように思うのですが。
A 国年法20条に併給できない規定があります
併給されない理由は国民年金法20条第1項にあります(条文は多少端折っています)。
第二十条 遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
この条文で、寡婦年金は遺族厚生年金と併給できないことがわかります。
この規定の中に「厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。」とあるので、遺族基礎年金は遺族厚生年金とは併給されることがわかります。
そして、この第1項は老齢や障害についても同様のことが規定されています。
この規定から、併給調整全体のルールとして、
65歳に達するまでは一人一年金の原則で併給されない。ただし、同一の支給事由で基礎年金と厚生年金を受ける場合は併給される
を覚えておいてください。
Q 国民年金の産前産後保険料について
産前産後免除制度のところで、「出産予定日・出産日の属する月の前月から4カ月間が免除される」とありますが、予定日と出産日の月が異なる場合はどちらを基準に考えればいいのてしょうか?その他のところは「出産日」となっていますが。混乱するので教えてください。
A 原則として予定日を基準に考えます
この免除制度は予め届出する場合と、出産後に届出する場合とがあります。「予定日」を考えるということは事前に届出された場合です。
ここで、実際の出産月が予定月と異なる場合であっても、当初の予定日ベースでの免除期間に変更はありません。ズレたとしても4ヶ月間の免除月数は変わらないからです。
ただし、例外として、例えば単胎妊娠で事前に届出たところ、現実は双子で出産したという場合には、免除の期間が増えるのでその場合は免除期間の変更を認めることとなっています。
Q 2022年秋試験、遺族給付の問題について

A 長期要件で年金額計算をするからです
まず、遺族厚生年金の年金額が300ヶ月みなしで計算されるということは、夫の死亡が短期要件に該当していることが必要です。
ここで、短期要件は
1 死亡時に厚生年金の被保険者であった
2 厚生年金の被保険者期間中に初診日があり、そこから5年以内に死亡した
3 1級又は2級の障害厚生年金受給権者が死亡した
という条件が必要になります。
そこで、夫の死亡は短期要件に該当するか検討すると、死亡時は国民年金加入なので1は非該当、3もそのような記載がないので非該当。
可能性がありそうなのは2となりますが、この方の初診日は「平成31年3月1日」となっています。この初診日は平成28年3月に厚生年金が終了したあとの、つまり退職したあとの初診日ということになり、2も非該当となります。
結局、この夫は短期要件に該当しないので、長期要件に該当することとなります。
結論として300みなしがされず、実期間で年金額が計算されることとなるわけです。
Q 振替加算について

A 年金制度に強制加入できなかった期間が1ヶ月でもある人には本体の金額とは別に加算による救済をします
加給年金と振替加算の関係ですね。
単純に後継という話ではありません。
そもそも、
旧法時代(昭和61年3月以前に生じた年金)の厚生年金制度における老齢年金に加算された加給年金は生涯にわたって加算されるものでした。
ところが、
昭和61年4月からは新法によって年金制度が大幅に改められ、加給年金の対象者になっていた専業主婦の方も第3号被保険者として強制加入させ、自分の老齢基礎年金をもらえるようにしました。
そこで、
新法における老齢厚生年金の加給年金は配偶者が65歳までで打ち止めとなりました。なぜなら、配偶者自身が自分の老齢基礎年金を65歳からもらえ、きちんとした老後の保障を受けられるからです。
ただ、
新法に切り替わった昭和61年4月時点で高齢の配偶者は老齢基礎年金の年金額が少なくなる可能性があります。年金制度に強制加入しない期間が長い人ほど、つまり、昭和61年4月時点で高齢な配偶者ほど老齢基礎年金本体の額が少なくなるからです。
そこで、
年金制度に強制加入できなかった期間が1ヶ月でもある人には本体の金額とは別に加算による救済をしてあげようとなりました。これが振替加算です。
加給年金は65歳で終わってしまうので、救済の加算は配偶者の老齢基礎年金にすることになります。
その境目は昭和41年4月1日以前生まれであり、つまり、4月2日以降の人は加算の必要がないので振替加算は出ないのです。
昭和41年4月1日生まれの人が20歳に達するのは昭和61年3月31日。1ヶ月だけ強制の期間がありません。だからここが境目になります。
Q 特老厚の男性の支給開始について

A ”試験のタイミングで60歳に達する人”という設定で考えます
特別支給の老齢厚生年金は基本知識問題で1問出ますが、毎試験ごと、
試験回のタイミングで60歳に達する人
の設定で出題がされます。
今年の試験は令和4年(2022年)3月ですので、このタイミングで60歳に達する人は昭和37年の3月あたりの生まれであり、2022年春試験においては、
昭和37年4月2日生まれ か 3月2日生まれ
の人の設定で出題されます。
この設定で男性を考えますと、全員が昭和36年4月2日以降の生まれの人なので、
「2022年3月試験の出題において」(男性は特老厚が受給できないので、出題はない)
という意味で 男性の報酬比例部分はなくなった とお話しております。
Q 年金生活者支援給付金の遺族給付金について

A 遺族給付金に市町村民税非課税の要件はありません
遺族給付金は
- 遺族基礎年金を受けている
- 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である
という2つの要件のみであり、「世帯全員の市町村民税が非課税」という要件はありません。したがって誤りとなります。
この「世帯全員の市町村民税が非課税」は老齢給付金のみの要件ですので気をつけてください。
勉強方法に関する質疑応答
Q 技能応用の最初の問題(問31・32)について

A 試験勉強に完璧さは不要
この問31・32は長年受験している私でも時間がかかり、かつ、間違ってしまうこともある問題です。
旧法時代の制度の話もそうですが、ここは年金の総合力が試される問題です。
したがって、現時点で制度の理解不足を認識しているということであれば、ここには敢えてこの問題に 勉強時間を掛けない というのが私のアドバイスです。
この2つの問題で4点 = 基本知識問題を2つ正解して4点。
どちらも同じ価値ということを考えれば、より、基本知識問題をパーフェクトにすべく、そちらに時間を掛けた方がコスパが良いです。
試験勉強に完璧さは不要です。割り切っていきましょう。

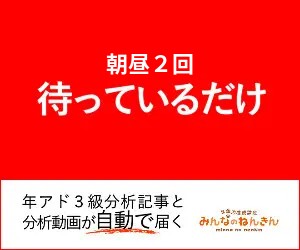



シモムー
みんなのねんきん主任講師